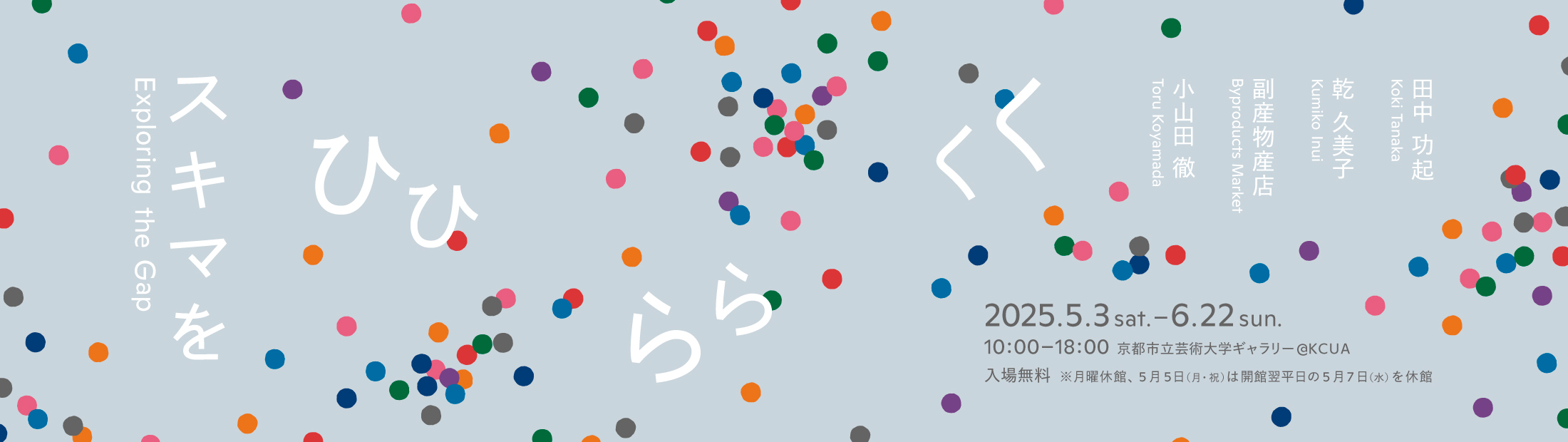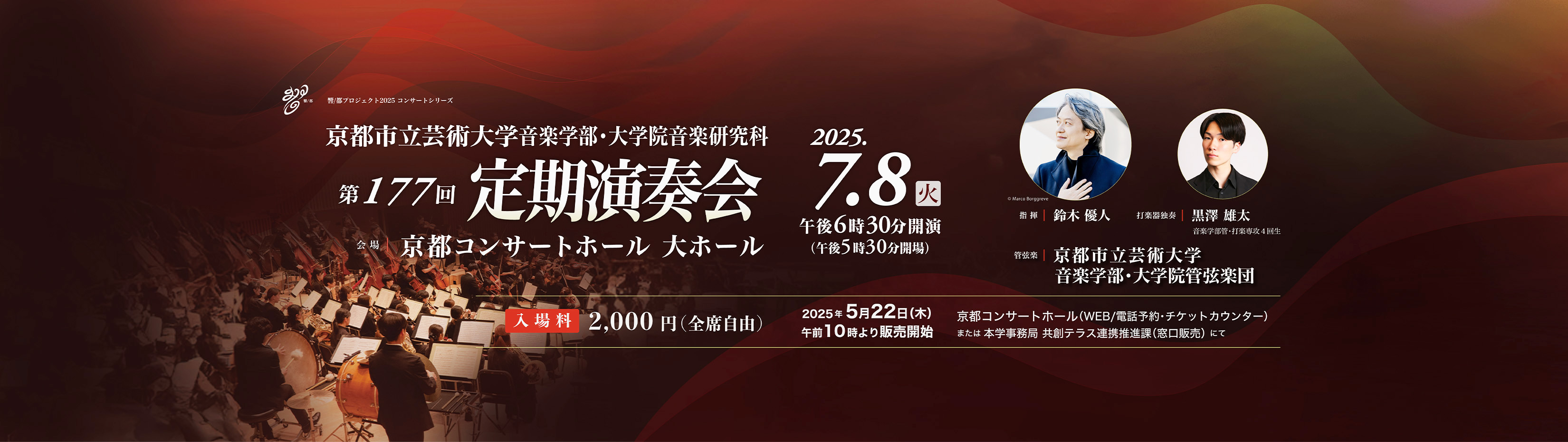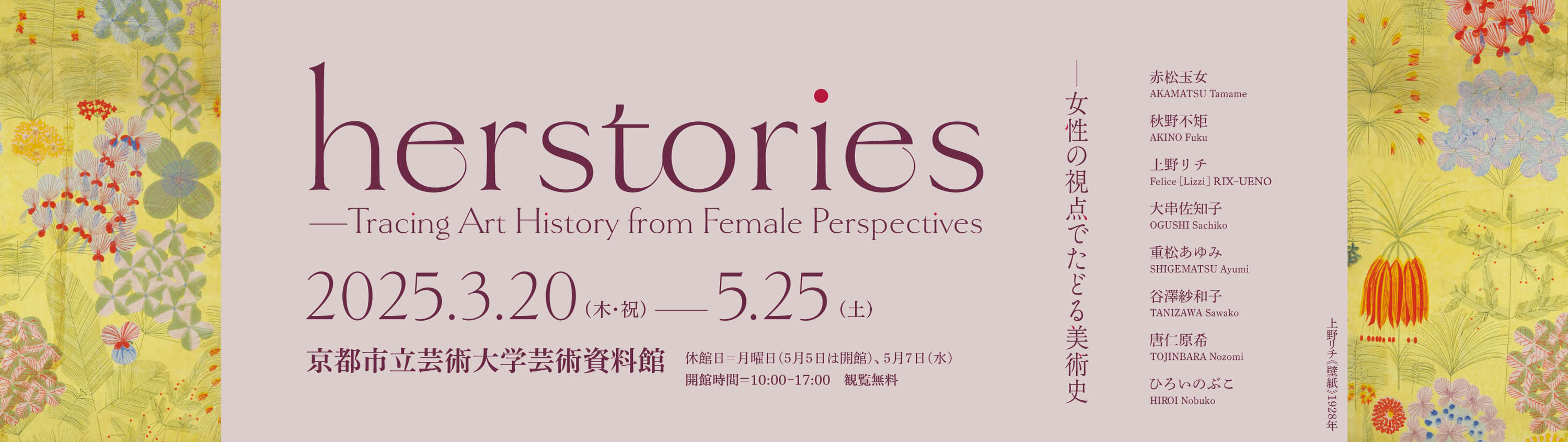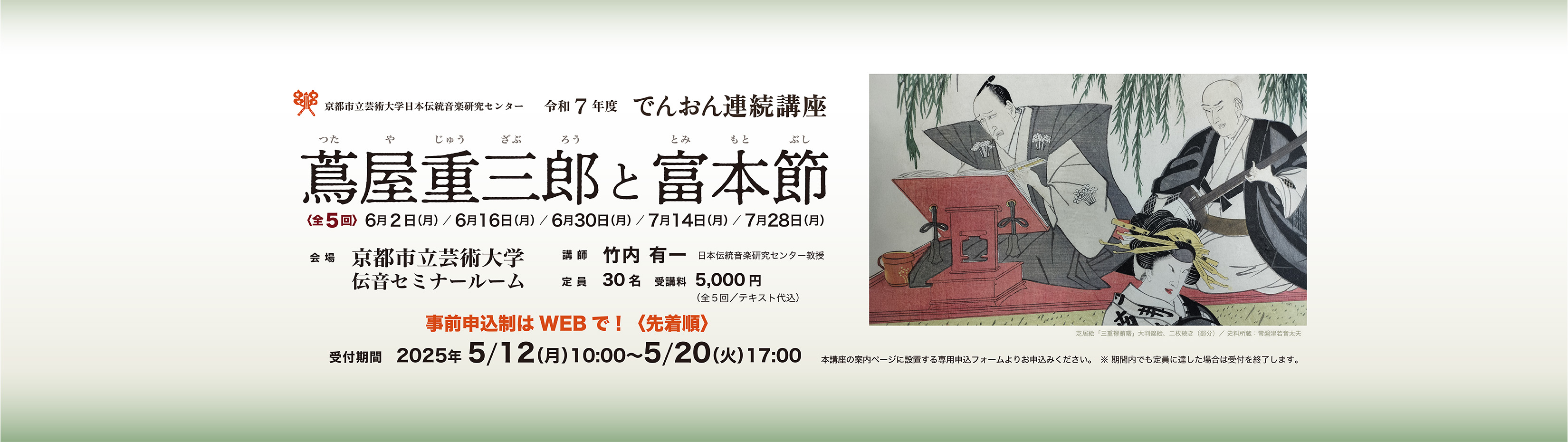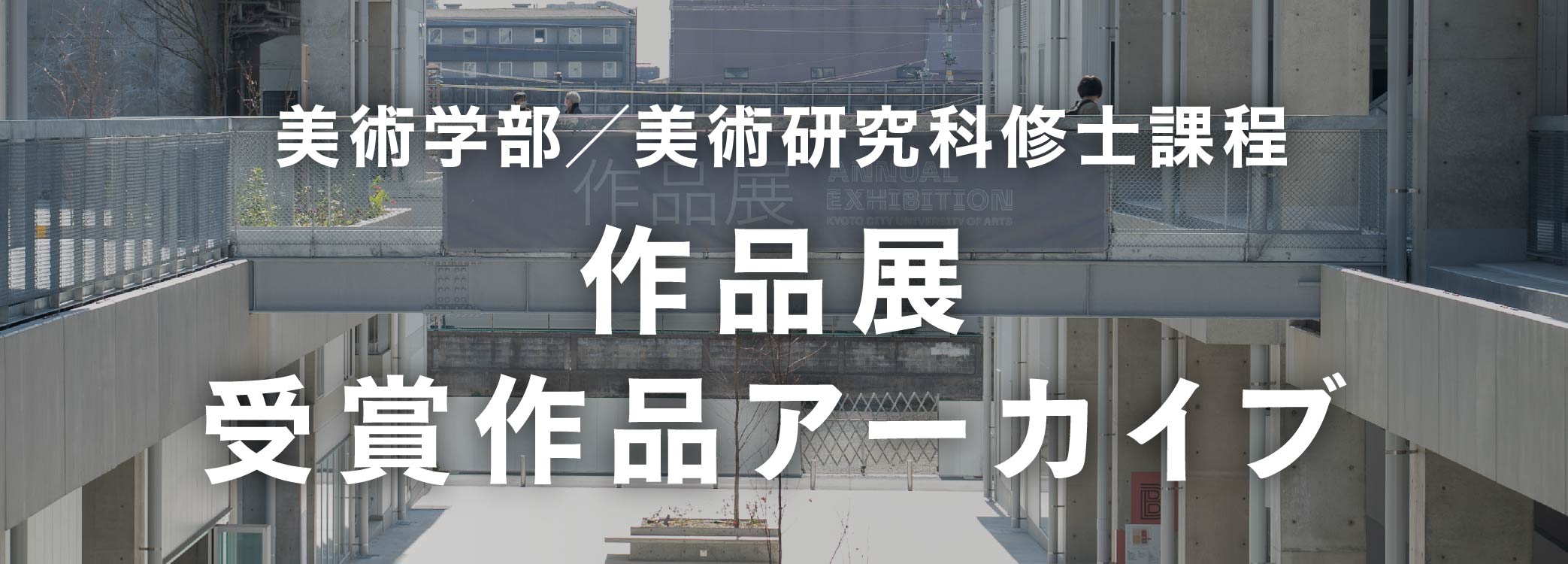ピックアップ
Newsお知らせ
-
 2025.05.02芸資研
芸術資源研究センター非常勤研究員公募のお知らせ
2025.05.02芸資研
芸術資源研究センター非常勤研究員公募のお知らせ
-
 2025.05.01
本学学生が第13回東九条春祭りに参加しました
2025.05.01
本学学生が第13回東九条春祭りに参加しました
-
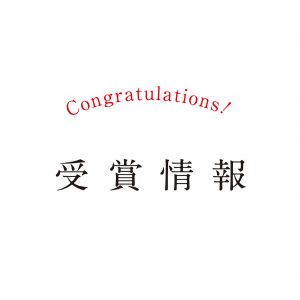 2025.05.01美術
【受賞情報】美術学部の朴蒼樹さんが「国際短編映画祭 ショートショート フィルムフェスティバル & アジア 2025」で入選
2025.05.01美術
【受賞情報】美術学部の朴蒼樹さんが「国際短編映画祭 ショートショート フィルムフェスティバル & アジア 2025」で入選
-
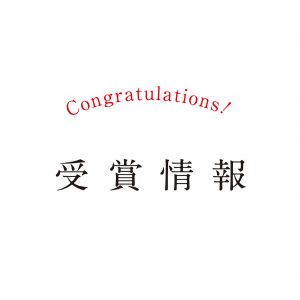 2025.04.25美術
【受賞情報】本学関係者が「第38回京都美術文化賞」を受賞
2025.04.25美術
【受賞情報】本学関係者が「第38回京都美術文化賞」を受賞
-
 2025.04.22
2025年度音楽学部オープンキャンパスの開催について
2025.04.22
2025年度音楽学部オープンキャンパスの開催について
-
 2025.04.22
【受賞情報】本学美術学部卒業生の外尾悦郎氏が「京都市文化芸術きらめき大賞」を受賞
2025.04.22
【受賞情報】本学美術学部卒業生の外尾悦郎氏が「京都市文化芸術きらめき大賞」を受賞
-
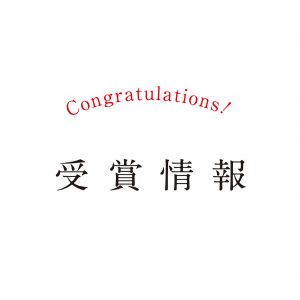 2025.04.22音楽
【受賞情報】大学院音楽研究科修了生の竹田理琴乃氏が「京都市文化芸術きらめき賞」を受賞
2025.04.22音楽
【受賞情報】大学院音楽研究科修了生の竹田理琴乃氏が「京都市文化芸術きらめき賞」を受賞
-
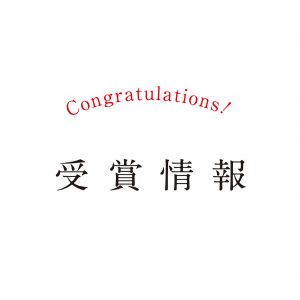 2025.04.22音楽
【受賞情報】音楽学部の阿部紗奈さんが「第19回セシリア国際音楽コンクール」で受賞
2025.04.22音楽
【受賞情報】音楽学部の阿部紗奈さんが「第19回セシリア国際音楽コンクール」で受賞